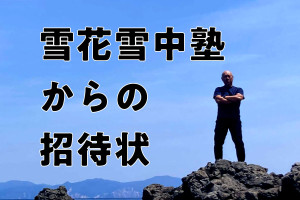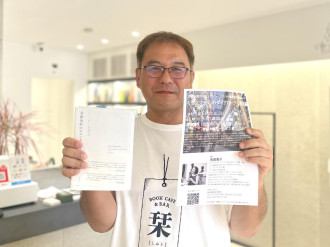【寄稿コラム】雪花雪中塾からの招待状1「大人になって学ぶ楽しさ」
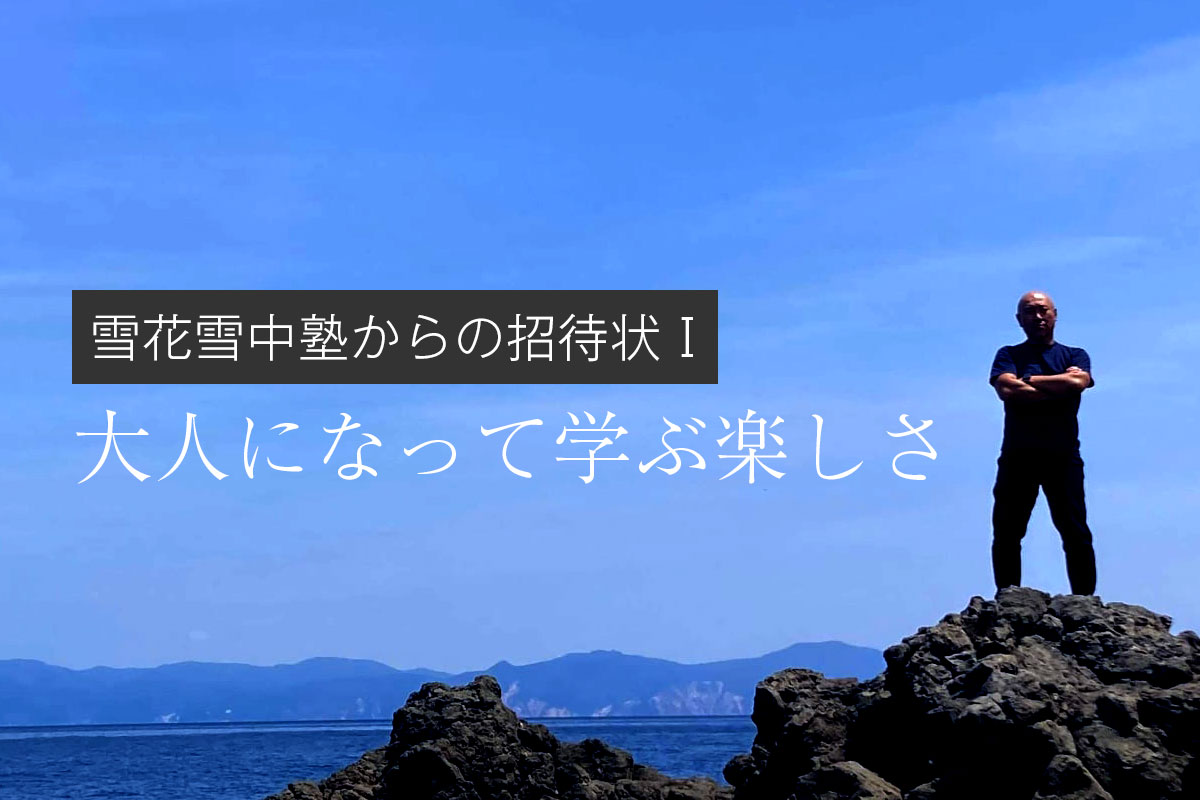
雪室りんごや雪下にんじんは、雪中でより甘くなると言われています。厳しい環境の中でより良い方に育つという特徴に重ね、今は隠れて見えない、地域の人財、産物、資源を、塾を通して見出したいという想いを込めた「雪花雪中(せっかせっちゅう)」。社会・地域課題の解決について、対話や講義を通じ、共に学び、考える場を作り、新ビジネスや地域おこしに取り組んでいく人財が育つよう「雪花雪中塾」のコーディネーター・講師のオール株式会社代表取締役の山崎宇充(うじゅう)さんが語る。
50歳で大学院に進めさせた言葉
社会に出てからの年月を重ねるほどに、人は「学ぶこと」から少しずつ距離を取るようになる。日々の業務、家族との生活、責任と役割に追われ、いつの間にか「知る喜び」よりも「こなす日常」に慣れてしまうからだ。
思えば私自身もその一人であった。多くの業界で新たな事業創出に携わり、成功も失敗も経験した結果、いつしか自分の中に一種の「高慢さ」が芽生えていたのだと思う。識者の意見や論調に耳を貸さず、常に自分の頭の中だけで世界を完結させようとしていた。そんな折、偶然目にした一つの講演が、私の思考を根底から覆した。
それはウォフォード・カレッジの学長、ベン・ダンラップ氏がTED(2007年)で語った「生涯学び続けること」というスピーチであった。老境に差しかかった彼が、若き日から今日まで「知ること」「考えること」「感じ取ること」を一度もやめなかった人生を、穏やかに、しかし力強く語る姿に、私は圧倒された。知識とは単なる情報の蓄積ではなく、人がより良く生きるための営みそのものである、その言葉は私の胸に深く突き刺さった。
そして私は、50歳を過ぎて大学院に進む決心をした。周囲は皆、耳を疑った。「今さら勉強してどうするのか」と。
しかし、私の中では迷いよりも好奇心が勝っていた。慣れ親しんだ経営や経済学の延長ではなく、あえて未知の領域である「社会デザイン」という分野を選んだのは、時代の変化を構造的に捉え、社会の未来をデザインする知を体得したかったからである。
ベン・ダンラップ: 生涯学び続けるということ(「TED」チャンネルより)
経済的尺度では測れないもの
今思えば、この選択こそが私の人生において最良の決断の一つだった。当初は、経済合理性だけで物事を考えてきた自分にとって、哲学、社会学、ボランティアといった学際的な知の世界は、まるで異国の地を歩くような感覚であった。しかし、知らないことを知ることの喜びは、やがて日常を覆い尽くすほどの熱量となった。学ぶほどに自分の中にあった先入観や固定観念が剥がれ落ち、世界が立体的に見えるようになる。これこそが学問の本質であり、「学び直し」の醍醐味なのだと、心から実感した瞬間だった。
仕事との両立は決して容易ではなかった。講義、レポート、研究、修士論文の執筆に追われ徹夜続きの日も少なくなかった。それでも、知的探究の楽しさが疲労や迷いを上回っていた。地方創生に関わってきた私は、研究テーマとして「若者の地方移住行動の心理的要因」を選んだ。2009年以降、都市から地方への移住が増加傾向にある現象を前に、私は純粋な疑問を抱いた。
便利な都会を離れ、なぜ若者はあえて地方に移り住むのか? フィールドワークを行い、数多くの移住者にインタビューを重ねるうちに、ある共通する感情に気づいた。
「東京に暮らしていると私がいなくなっても何の影響もないように感じていた。でも、地方では地域の人たちが私を必要としてくれる。」という言葉に出会ったとき、私は、はっとした。そこにあったのは、必要とされる自分、「自己承認欲求」であった。
便利さや所得水準といった経済的尺度では測れない、人が「生きている実感」を得る場としての地方。移住者は、社会的ネットワークの希薄な都会では満たされなかった承認欲求を、地域との関わりの中で再び見出していたのである。
この気づきは、私の地方創生観を根底から変えた。 地方の再生とは、大規模な投資や制度改革だけではなく、「人と人との関係性の再設計」にこそ本質がある。 小さな社会の中で、互いが互いを必要とするという小さな循環。 そのバランスが少しずつ積み重なることで、やがて地域が自律的に変化していく。 そんな未来像について、修士論文を通じて見出した。

何歳になっても出会うことができる
大学院の二年間は、年齢も背景も異なる仲間たちと学び合う日々だった。 社会人としての経験を持つ者、若くして起業を目指す者、教育現場に立つ者。 それぞれが異なる視点を持ち寄り、互いの考えに触発されながら議論を重ねた時間は、何ものにも代えがたい財産となった。 修了後、彼らの多くは職場や地域活動の中で、学んだ知を実践している。 学問は机上で終わらない。 現場に還元し、社会を動かすためにこそ存在するのだ。
ベン・ダンラップ氏は講演の最後でこう述べた。 「知と経験に対する決して消えることのない不屈の欲求が、思い描く未来の形をつくる」と。 私にとってこの言葉は、単なる名言ではなく、人生の指針そのものとなった。 知を求め続けることは、過去の自分を更新し続けることでもある。 人は何歳になっても、新たな世界に出会うことができるのだ。
その想いを形にしたのが、青森商工会議所と共に立ち上げた「人財育成 雪花雪中塾(せっかせっちゅうじゅく)」である。
雪花とは、雪(氷)を顕微鏡で見ると咲く花のように見える。 良く見れば、この地にも花のある人材は多くいる、という意味。 雪中とは、雪室りんご、人参など、雪の中で貯蔵すると熟成される、という意味を、厳しい環境の中でも静かに芽吹く人の力、として、これを塾名とした。
雪花雪中塾では、単なるスキルや知識の獲得ではなく、「問いを立てる力」「構想する力」「共に考える力」を重視している。 学生だけでなく、社会人が再び学び、地域の課題を自分事として捉え、仲間と共に思考する場をつくりたいと考えている。 世代や立場を超えて、共に学び、共に考え、共に行動する「共創の場」である。 人生経験を積んだからこそ見える世界がある。 学び直しは、人生をもう一度編集することなのだ。

雪花雪中塾からの招待状6「-雪花雪中塾からの招待状-」(2025年12月29日更新)
雪花雪中塾からの招待状5「未来予測からアクションを考える」(2025年12月26日更新)
雪花雪中塾からの招待状4「多視点で磨く思考力」(2025年12月10日更新)
雪花雪中塾からの招待状3「本当の学びとは」(2025年11月19日更新)
雪花雪中塾からの招待状2「雪花雪中塾誕生秘話」(2025年11月10日更新)
30代でIT、メディアの上場会社で役員を歴任し、40歳で独立。 IPO支援、新規事業開発、事業再生、地方創生事業など幅広い分野でコンサルタントとして実績を積み上げる。 2024年9月に青森にオール株式会社(Aomori Legacy Linc = ALL)を仲間と設立。 人財育成 雪花雪中塾 コーディネーター 兼 講師 神奈川大学 客員研究員。TECH HUB YOKOHAMA メンター。